北上小学校5年生のヨシ紙漉き。
- riasnomori
- 2020年5月1日
- 読了時間: 2分
昨年12月、自分の刈り取った北上川のヨシを素材に、分の手で和紙を漉きます。この春6年生になって1年学校生活に励んで、来年3月。これが卒業式で受け取る証書の紙になります。

みんなが刈って束ねたヨシを「りあすの森」スタッフが石川県は能登半島の輪島市へ持っていきました。それを紙漉きの素材に加工してくれたのは、いつもの遠見和之さん。「能登二行(にぎょう)和紙」の職人です。今年は能登も暖冬で雪がさっぱり積もってないとか。でも運転はきっと楽であったことでしょう。「漉き船」と呼ばれる杉の厚板で組んだ水槽も、今年もワゴン車に積み込んで、来町してくださいました。 玄関ホールにこの漉き船を据え置き、水を張って、ヨシを細かく細かく粉砕した繊維のペーストを溶かします。そして繊維を均一に広げるため(接着のためではありません、と遠見さんはいつも説明してくれます)の「のり」を加え、とろりと水にゆきわたらせます。 卒業証書サイズの特製「簀(す)」を、両手を伸ばして遠い水面へとぷん、と差し込んで手前にすくい上げるんですね。簀を持ち上げると水がじゃわじゃわ滴り落ち、少しずつ水が切れてきます。からみあった繊維が紙の形に残ります。この時点で、厚みは5mmくらい。その簀を裏返して(簀についたヨシ紙は剥がれ落ちないんですよ)、置き台の上に伏せ、簀だけを剥がすと、ヨシ紙だけが残ります。この上に布の「さらし」を挟み、次の人の紙を置き重ねてゆくのです。私が漉いた紙には、ちゃんと小さな名前紙をおきます。(写真にはキャプションついてます) とろん、たぷんと揺れ動く水から、すくい上げて紙になる、という手順がいつも不思議です。遠見さんは道具とともにこの湿ったままのヨシ紙を持ち帰り、水を切り、乾かして完成してくれるのです。さあ次は6年生。健康に気をつけながら勉強に、スポーツに、遊びに。一度しか無い一年、家族とおもいきり楽しんでくださいな。














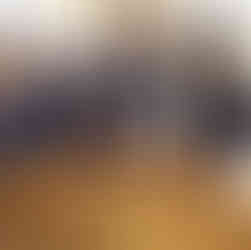












コメント